 |
|
 |
|
|
RI�e�[�}�@�gThe
Future of Rotary Is in Your Hands�h |
|
|
��Q�V�W�O�n��K�o�i�[ |
|
��P�T�Q�V����T�� |
|
�Q�O�P�O�N�S���P�Q���i���j |
|
|
|
|
|
|
| ����� | ���h�l�Q���̂���B |
| �����c�A�ĎR��t���ڕW�B���˗��B | |
| ���U���Q�X���i�j�J�×\���P�O���[�v�O����o�ȋ`���� | |
| ��F�܊}�A����F��{�A�����F���c | |
| ���N�x��F�H���A���N�x����F���c�i�d���j�A���N�x�����F�V�� | |
| ���N�x�K�o�i�[�⍲�F�X�A���N�x�K�o�i�[�⍲�t�����F�{�{ | |
| �ȏ�V���̂��Q���X�������肢�v���܂��B | |
| �������� | ���K�o�i�[���M�i���P�O�j��́B |
| ���o�ȕ� |
|
���o�ȕ� |
��� | �o�� |
�Ə���� �o�� |
�{���̏o�ȗ� | �O�TҰ����ߑO | �O�TҰ����ߌ� |
| �P�W�� | �P�T�� | �U�� | �W�W.�W�X�� | �W�R.�R�R�� |
�X�S.�S�S�� |
| �����[�N�A�b�v���ꂽ��� | |
| ��P�O���[�v�O����܊}��A���c��� | |
| ���E���C���^�[�A�N�g�ψ���{�{�ψ��� | |
| �h�l���܊}�A��{�A���c�A���A���c�A�H���A�X�A���c�A���ˁA�V���B | |
| ���j�R�j�R�{�b�N�X�� | ||
| �P | �܊} �m�u�N | �I�[���N�A�悤�����B�i�䂳��A�{���X�������肢���܂��B�h�l�����낤�l�ł����B |
| �Q | ��{ ���F�N | �����͊����ł��ˁB�i�䂳���N�Ԃ�̘b�ł��ˁA��낵����肢���܂��B |
| �R | ���c ���N | �i�䂳��A��b�X�������肢���܂��B |
| �S | �^�� �p��N | �i�䂳��A��b��낵�����肢�v���܂��B |
| �T | �O�� �m�j�N | �i�����̑�b�Q�l�ɂ������ł��B��낵���B |
| �U | ��� �F��N | �i�䂳��A�{���̑�b��낵���B |
| �V | �勴 ���v�N | �i�����A��b��낵�����肢�v���܂��B |
| �W | �H�� ����N | �i�䂳��A���J�l�ł��B |
| �X | �i��s�m�j�N | �{���͋X������肢�v���܂��B |
| �P�O | �{�{ ���u�N | �i�䂳��A��b�y���݂ł��B |
| �P�P | ���c �����N | �i�䂳��A��b�y���݂ɂ��Ă��܂��B |
| �P�Q | �X �E�l�N | ����̂h�l����J�l�ł����B�i�䂳��A�{���͑�b��낵���B |
| �P�R | ���� �ܘY�N | �i�䂳��A��b���̂��݂ɂ��Ă��܂��B |
| �P�S | �V�� �@���N | �i�䂳��A�{���͂�낵�����肢���܂��B |
| �P�T | ���� �����N | �o�[�X�f�B�v���[���g���肪�Ƃ��������܂��B |
| �i�䂳��A�u���{�̓`���v�̑�b�y���݂ɂ��Ă���܂��B | ||
|
�O���v |
�U�S�T,�O�O�O�~ | �{���v | �P�X,�O�O�O�~ | �v | �U�U�S,�O�O�O�~ |
|
|
| ���ψ���@�H���e�r�ψ��� | ||
| �t�̐e�r���s�ē� | �����F�����Q�Q�N�T���P�Q���i���j�`�P�R���i�j | |
| ���F�T���~ | ||
| ���� | ||
| �T���P�Q���i���j | ||
| ���{��7:00�������X�����������l�h�b����8:45�C�V���r�`�i�x�e�j9:00 | ||
| �����܌Γ��H��������������10:30�J���o�`�x�e10:45����11:45�z�K�r�`12:00 | ||
| ����12:50�ѓc�i���H�j13:40����14:10�o�D �V�����C��������15:00���������H�� | ||
| ����16:00��ؑ]�u�z�e���ؑ]�H�v�h�� | ||
| �T���P�R���i�j | ||
| �u�z�e���ؑ]�H�v9:00����9:20���ďh�i�U��j10:20����10:50�n�ďh�i�U��j11:50 | ||
| ����12:20�Q�o�̏��i���H�E�U��j13:30�����q�P�X���������q���ٌo�R | ||
| ����15:00�z�K�r�`�i�x�e�j15:15����16:15�J���o�`�i�x�e�j16:30����18:00�C�V���r�`18:15 | ||
| �������l�h�b�������X�����z�Ԋe�n19:30 | ||
| ����b�u���r�ɂ��� �v�@�i�� �s�m�j��� | ||
|
������
�@�e���������A�����ԑr�ɕ����邱�ƁB �������@�ߐe�҂̎��ׁ̈A�߂�w�Z���x��őr�ɕ����邱�ƁB�܂��A���̂��߂̋x�ɁB
�������@�ߐe�҂����S�����ہA�����̔Z���ɂ�����������r�ɕ����邱�ƁB |
||
| �u���v�Ɓu���v�̈Ӗ� | �u�����i���ӂ��j�v�́u�����i�Ղ����j�v�Ƃ������܂��B��ʂɂ́u���r�i�ӂ����j�v�ƌĂ�Ă��܂��B | |
| �u���i���j�v�Ƃ́A���҂̂���������ނ��Ƃł��B�l�̎��͂����ꂽ���̂ƍl�����A | ||
| ���҂��o�����g���́A�����ԁA���퐶�����牓������A�g��T�܂˂Ȃ�܂���B | ||
| ���̊��Ԃ���Ɂu�����v�ƌĂсA���݂ł́A���e�̎���߂���ŋސT������Ԃƍl���Ă��܂��B | ||
| �u���i�Ղ��j�v�Ƃ́A�r���̂��ƂŁA�g���Ɏ��҂��������Ƃ��A�����ꂽ�̂�r���ɕ��ŁA | ||
| �����ԁA�s����T�݁A�g�𐴂߂邱�Ƃ̈Ӗ��ł��B | ||
| �u���v�Ɓu�� �v���܂߂āu�r�i���j�v�Ƃ������܂��B�����̊��Ԃ��u�r���v�ƌĂт܂��B | ||
| ���݂ł́A�u�r���v�͌c����T�ފ��ԂƂ���Ă��܂��B | ||
| ���Ă̊����߂ł͒����̉e���ŕ���̎��́u���v������49���A�r�̊��Ԃ́A����1�N�Ƃ���Ă��܂��B | ||
| �r�̊Ԃ̐H���ɂ��Ē����̋V���̌ÓT�ł���w��L�x�u�ԓ`�v�ɂ́A�u����̑r�ɂ�3���Ԃ͒f�H�ŁA3���ڎ��҂����ɔ[�߂čՂ������Ƃɏ��߂Ċ���H���B | ||
| �Ȍ���e�тɐ�����Ŗ���H�ׂȂ��B1�N�̏��ˊ����I����āA���߂Ė�E�ʕ���H�ׂ�B | ||
| ������3�N���̑�˂ɏ��߂āA���A�����������v�Ƃ���܂��B | ||
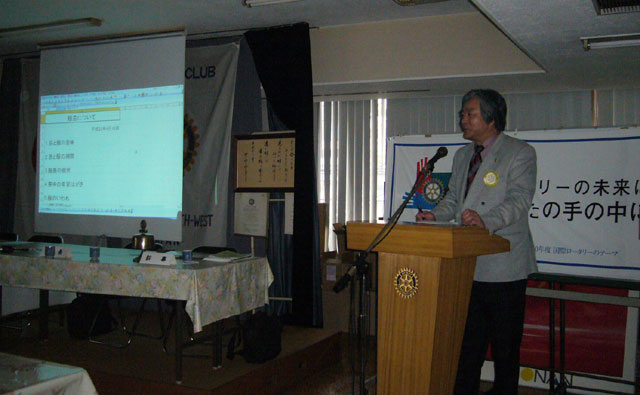 |
�S���Ȃ������𖽓��ƌĂсA���N�߂����Ă��邻�̊������ˌ������ƌĂт܂��B | |
| ���̏ˌ������ɂ��ẮA�u�w��L�x�ɂ��ΐe���S���Ȃ��ď\�O���̍Ղ��u���ˁv�i������j�E��\�܌��̍Ղ��u��ˁv�i�O����j�Ƃ����B | ||
| ���̂悤�Ɉ���N�E�O�N�̌������u�ˁv�Ƃ����̂ŁA����Ȍ������ɂȂ���ďˌ��Ƃ����B | ||
| ����͉䂪���̏K���̌����K�킵�ɂ����̂ł���B�v�Ƃ���܂��B | ||
| �u�ˁv�Ƃ����̂́u�����킢�v�Ɠǂނ̂ł����A����͋����������ċg���ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ł����Ă���̂ł��B | ||
| ���Ȃ݂ɉ䂪���ł́A����7�N�ɏo���ꂽ�吭���z���́u�������v�ɂ��ƁA | ||
| �r���𒅂Č̐l�̖������F���ĐT�܂��������Ă�����Ԃ̕����͕���̂Ƃ���13���ƂȂ��Ă��܂��B | ||
| ��قǂ̒����̏��˂̊����ƍ����Ă��܂��B�@����͒����̌Ăѕ������̂܂ܓ��{�ɓ`����ꂽ��ł����A | ||
| �u���ԗv���ڂ�����悤���v�Ƃ��������ɂ́u���������傤�����v�Ƃ���܂��B | ||
| ����͊����͖�������܂����A���̌��̊����́u�����̌��v�Ȃ̂ŁA | ||
| �u�������v�Ƃ����A����𗪂��āu�������傤���v�Ƃ����܂��B | ||
| �������u�����v�͔N�̏��߂́u�����v�i�ꌎ�j�ƊԈႦ�₷���̂ŁA | ||
| ��̒����̗�L�ɂ�鏬�ˊ��E�吳�����Ƃ��āu�ˌ��v�Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B | ||
| �܂������Ƃ����̂́w�o���傤���傤�x�Ɏ��S�̓����u���ߓ��߂����ɂ��v�Ƃ���A | ||
| �߂͉߂���Ƃ������ƂŁA����̎������߂����������Ƃ����Ӗ����炱��𗪂��āu�����v�Ƃ����܂��B | ||
|
�u���v�Ɓu���v�̊��� |
�����̕��K�͔��ɌÂ��A�����I�̌㔼�A�V���V�c������̑r�ɕ������u�d���v�̋L�^���c���Ă��܂��B ���������x�����ꂽ�̂́A����701�N�ɁA�����V�c�̑�߂̑r���߂����߂Ăł��B ���̌�A�{�V�߂Ƃ��ďC������Ă���A�]�ˎ����ʂ��Ċ����̊��K�͎p����A�������N�ɁA�������z���̕����߂����肳��A�e���ʂɊ����̊��Ԃ���߂��܂����B ����̑r�̏ꍇ�A���̊��Ԃ��\���A���̊��Ԃ�13�����A�܂��v�̏ꍇ�́A����30���A����13�����Ȃ̂ɑ��āA�Ȃ⒄�q�́A����20���A����90���ƁA�r�̊��Ԃɑ傫�ȍ�������A�ƒ����x�̌X���������A���݂ɓK�p����ɂ͖���������܂��B ���݂ł́A���������d�����x�߂�������x�ɂ́A�v���Ȃ�10���ԁA����A�{����ň�T�ԂƂ������Ƃ���ŁA���̊��������Ԃ͈�ʂ̉�Ђɂ��������Ă���܂��B�����ɂ́A���������Ԃ��߂���ƁA����̐����ɖ߂�̂����ʂł��B ���݂ł́A��ʓI�ɂ́u���v�̊��Ԃ܂�u�����v�́A�������܂ł̊��ԂƂ���A�����ł�49���܂ŁA�_���ł�50���Ղ܂ŁA�L���X�g�����Ɋ������͂���܂��A1�����̏��V�L�O���܂łƍl�����Ă��܂��B �����āA�u���v�̊��ԁA�܂�u�r���v��1�N�ԂƂ���Ă��܂��B |
|
|
�� �r���� �� |
�r�Ƃ͐l�̎���A�e�����Ƒ��̎��𓉂�ŁA����̊��ԗV�т�������݁A�܂������f���ĉƂɋސT���邱�Ƃ������܂��B���������݂ł͑��V�E�@�v�ȊO�͑r����E���A���i�Ɠ�������������悤�ɂȂ�܂����B �������r���͂ł��邾���h��ȃ��W���[��V��������A�������̏o�Ȃ�_�Ђ̎Q�q�A�N�n�Q����T����̂����ʂł��B |
|
|
���������� |
�����������K��ɂ��ƁA�������Ԃ͎��̂悤�ɒ�߂��Ă��܂��B
�@���@�z��ҁd�d�d�i10���j
�@���@���@��d�d�d�i�V���j
�@���@�q�@���d�d�d�i�T���j
�@���@�c����d�d�d�i�R���j
�@���@�Z��o���d�d�i�R���j
�@���@���d�d�d�d�d�i�P���j
�@���@�f���E�f��d�E�i�P���j
|
|
|
���r���̔N��͂��� |
�r���ɂ͔N�����o�����A�N�ꌇ��̈ē��͂�����12���̂͂��߂ɓ�������悤�ɏo���܂��B �N�ꌇ��́A�̐l�ƔN�����������Ă����l��Y��Ȃ��悤�ɂ��܂��B |
|
|
�����̂���� |
�r���͋����Ƃ������A����E�Ȏq�A�e�ʓ��́u�����v�̊Ԃ́A�r���𒅂邱�Ƃ���߂��Ă��܂����B�u�����߁v�ɂ���u���v�Ƃ͑r���𒅂�ׂ����Ԃ̂��ƂŁA���҂͐_���Ɍg��邱�Ƃ͋ւ����A�܂������ɂ��Q���ł��܂���ł����B���r���Ԃ������āA�����E�����Ƃ������Ƃ����A�͌����O�ōs�Ȃ��܂����B���̂悤�ɁA���Ƃ��ƈ⑰�݂̂��r���𒅂邱�Ƃ��`���Â����Ă���A��ʉ�҂͑r���𒅂��߂͂Ȃ������̂ł����A�吳�������A��ʉ�҂��r���𒅗p����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��⑰���r�̊��Ԃ�ʂ��Ē������邱�Ƃ͂����A���V�̎��ɂ̂ݑr���𒅂�悤�ɕς���Ă��܂����B | |
|
�u���v���Ӗ����鍕 |
���{�ł́A�r���͍��œ��ꂳ���Ⴊ�����B���������������ȑO�ɂ����ẮA�r���͔��ł������B�����V�c�����V����A���Ăɍ��킹�đr�������Ƃ���悤�ɂ��ꂽ�B | |
| ����̓��{�ɂ����āA�r�������┖�n�F����ʓI�ł���B�܂��A�a���̏ꍇ���r���Ƒr��̔z��҂����𒅗p���邱�Ƃ�����B�t�����Ȃǂ̔h��ȐF�͂ӂ��킵���Ȃ��Ƃ���Ă���B | ||
| �{���r���Ƃ́A�⑰���u�r�ɕ����Ă���v�Ƃ������Ƃ��Ӗ�������̂ŁA�����Ɨ����ƌĂ����̂�����A�e���͐����̂��̂𒅗p����B | ||
| �L���X�g���n�̏@�h�ł́A�x�[���ŏ����̊�����Ƃ��r�̐����Ƃ����B | ||
| �r���̉p���́A���[�j���O�E�h���X(mourning dress)��[�j���O�E�N���[�X(mourning clothes)�ł���B | ||